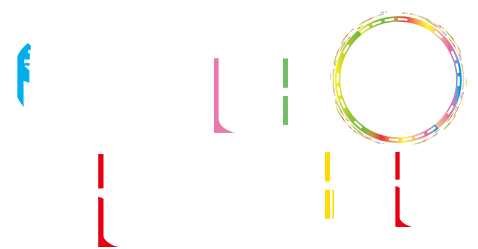
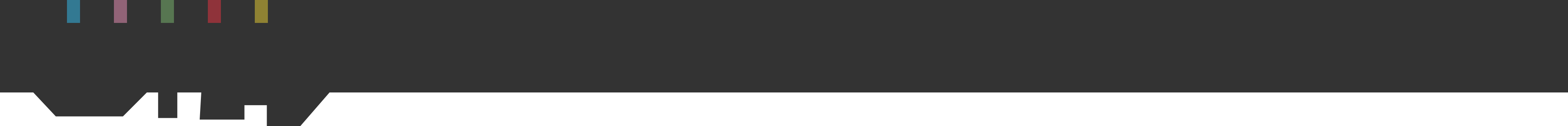
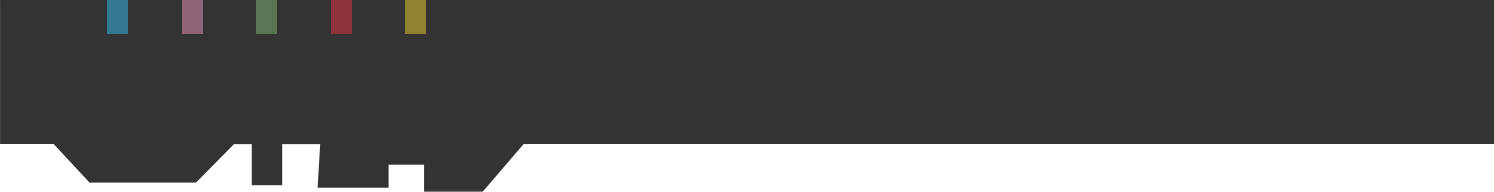

アリス短編ストーリー
Gunnolf.Bjorn作
ChatGPT翻訳(一部ブラウン調整)
Alice – 不思議の国の終わりから新たな始まりへ

通りの中で足跡の音が大きく響いていた。荒れ果てた道路には、落ちた建物の瓦礫が予測不可能な障害物となって広がっている。そこを、一人の人物が必死に駆け抜けていた。彼女の荒い息遣いや高鳴る心臓の音が耳を突き、灰色と紫の暑さに包まれながら必死に逃げようとしていた。しかし、彼女は何から、または誰から逃げているのか、覚えていなかった。右へ、左へ、再び右へ。彼女の文明の崩れた建物の死骸が、見知らぬ方向へと彼女を誘導し、周囲は絶望的な荒廃となっていた。彼女は、最後に一度だけ後ろを振り返って追ってくる者がいないことを確認したが、そのせいでつまずき、濡れたなコンクリートにバタンと倒れた。薄い雨水が彼女の転倒の音を静めた。彼女は息を切らしながら立ち上がり、前に進もうとしていたが…
バキバキ、バキバキ…
重い足跡によってコンクリートが粉々にされる雷鳴のような音が彼女を恐怖で固まらせた。その音は次第に近づいてきた。彼女が先ほど傷つけた膝からの突然の痛みがなければ、彼女はそのまま通りの中央に留まり、近づく恐怖に飲み込まれていたかもしれない。彼女は全ての力を使って瓦礫の後ろに隠れ、耳を手で覆い、恐怖の嵐が通り過ぎるのを願いながらゆっくりと前後に揺れた。
バキバキ、バキバキ、バキ…
突然、すべてが静まり返った。雨のぱたぱたという音だけが聞こえていた。しかし、彼女はまだ見る勇気がなかった。これは仕掛けに違いないと彼女は考えた。だから、彼女は膝を抱えて隠れたまま、何分もの間、音も立てずに待っていた。やがて、彼女の中の勇気が戻り、前に進むことを彼女に促した。しかし、彼女が隠れていた場所から這い出すと、膝がふらついている中、大きな影が彼女を覆い尽くした。静けさは一瞬で消え、恐怖、苦痛、痛み、そして悲しみの音が耳をつんざき、死の強烈な臭いで空気が満ちた。これが最後だった。もう逃げることも、生き残ることもできない。彼女はその恐怖に立ち向かわざるを得なかった。彼女は急に振り向いた。
アリスは悲鳴をあげて目を覚ました。彼女の顔は赤く、熱い涙が頬を伝って流れ落ちていた。彼女がかつて知っていて、大切に思っていた何百人もの人々の無残な姿が、彼女の心に押し寄せてくる。その夢はまだ鮮明で新しく、彼女の心の傷を生々しく保っていた。生き残ったことへの罪悪感、自分の力を最大限に使って故郷の世界を救わなかったことへの重い罪悪感は、若いアリスにとって、特に今、彼女がアークに安全に避難している今、ひどく重くのしかかっていた。毛布をしっかりと自分のまわりに巻きつけ、その柔らかな温もりと背中に感じるその重みの心地よさに安堵を感じた。
夢の中の恐怖が和らぎ、アリスが自分の居住区を出るのに十分な気力を確保するまでには、数時間を要した。それでも、彼女が船の共同食堂に足を運んだのは主に空腹のためだった。アーク内部の疑似的な一日のサイクルによれば、まだ早朝であるため、少なくとも混雑はしないだろうという事実は、彼女に少しの安堵をもたらしていた。しかし、その数が少ないにもかかわらず、食堂にいる生存者たちの多様性には、少し驚かされた。しかしこの驚きはすぐに、侵略次元という厄介者たちがすでに荒廃させてしまった数多くの世界がどれほどいるのか彼女に改めて知らしめ、憂鬱さとわずかな罪悪感に変わった。
静かに、機械的に食事を取り続けた。食べ物の味と香りは、確かに空腹の辛さを和らげていたが、それ以外の慰めは何もなかった。
「聞いたかい?最後に訪れた惑星で招かざる客を拾ったそうだ。」
アリスの耳が少し動いた。二人の人物が、物陰でひそひそと話しているのを聞いていた。


「ありえないよ。そこには生命体は一切いなかったという話じゃないか。それに、もし『連中』の手先が入ってきたものなら、アークのセキュリティバリアによってバラバラにされていただろうさ…」
言葉が尽きたような、どこか悲しげな男の声はそこで途切れた。
「馬鹿だね」と、彼の女性の影のような相手は、辛辣な口調で切り返した。「じゃあ、みんなが抱えるその暗い夢はどう説明するのかい?“悪夢を見るのは当然だ”って言う前に、最下層から始まって、一定のパターンに沿って上層にも広がっているってこと、忘れるんじゃないよ」
彼女の相手が口を挟もうとしたが、きっぱりと遮られた。
「お前が協力しようとしまいと、私はこれを解明するつもりだよ、マッドハッター。それが侵入できるほど惨めで小さな侵略次元の尖兵なら、復讐—いや、正義を執行するチャンスを逃す気はない。」
彼女はその最後の言葉と共に、怒って立ち去った。それから、男が立ち上がり、アークの薄暗い回廊へ向かった彼女の後を追いかけた。彼は一つ短くため息をついて、まるで手品師のように姿を消した。
アリスは、自分の耳に入ってきた言葉を信じられなかった。この船に侵略次元がいるなんて?いや、いや、いや、それはあり得ない。ここは安全のはずだ!彼女たちは侵略次元の脅威から生き延びたはずだった。このままでは皆、死んでしまう!食べられて、根絶やしにされて、虐殺されてしまう!いや、いや、いや、イヤ!アリスは感情が高ぶり、食べかけの食事を放り投げ、心の混乱から体が震えていた。
アークの日中サイクルが「朝」に切り替わった瞬間まで、アリスは現実に引き戻されなかった。難民たちが食糧を求めてダイニングホールに入ってくる賑やかな様子が、彼女を現在の状況に引き戻したのだ。
新たな決意を胸に、彼女はホールから飛び出し、部屋に戻って準備を始めた。彼女は決断した。自分の故郷でためらったようなことはしない、この潜む脅威を見つけ出し、自分自身の力でそれを根絶するのだ。以前は失敗したけれど、アークの生存者たちを守るためには、今度は失敗しない。
船の日中サイクルが再び夜時間に移行すると、アリスは準備を整えてこっそりと自分の居室を抜け出した。壁から壁へと身を隠しながら進む彼女は、深夜中みかけた見知らぬ人たちが「怪物」は夢の中でのみ顕現する、と囁いていたことを思い出し、‘就寝時間’中に廊下をパトロールする覚悟を決めた。
彼女は警戒を怠らず、耳を動かして、何か問題の兆候を察知するための微かな音を聞き分けようとしていた。具体的に何が聞こえてくるのかは分からなかったが、時が来たときにそれを認識できることを切に願っていた。
一時間が過ぎた。その後もまた一時間、更にもう一時間、パトロールで何も見つからない時間が長くなるにつれて、彼女の緊張は高まっていった。「果たして、ただの悪夢だったのかもしれない」と、自分自身の悪夢の恐ろしさがぶり返りそうな感覚に思いを馳せながら、彼女はひとりで考えた。その思考が彼女の足取りを遅らせ、最終的にはアークの数多くの交差点の一つで、彼女の動きは完全に停止した。
運命だったのか、単なる幸運だったのか、彼女が立ち止まっていなければ、間違いなく南側の廊下でちらりと光った紫の閃光を見逃していただろう。そしてそれが消えてしまう。彼女は「それだ」と思った。頭がぐるりと回り、本能が犯人であり潜在的な脅威を見つけたと告げている。しかし、それを認識するのは早かったものの、その意志に従うためには彼女の体がもう一秒必要だった。彼女が自分の力を使うことにためらいを感じ、一瞬の間、動きに疑いが生じたのだ。
廊下を駆け下り、彼女は影のような存在を追いかけた。それは大きく、形の定まらない、ほとんど形を成していないように廊下を滑るように進む。時折、その後を追うのに苦労したが、何となくいつも再びそれを見つけ、本能が彼女を導いた。
その追いかけはほんの数分間だったが、アリスにとっては何時間も感じられた。ついに‘怪物’を袋小路で追い詰めた。その場に留まりながら、その存在はゆっくりと回転し始めた。その無形の黒い霧のような体から、恐ろしい紫色の目がアリスに向けられ、緋色の鋭い歯が光った。低い音がその無形の形から発せられ、2つの存在が見詰め合う中で、それはどこか唸り声のように聞こえた。アリス自身も目をそらさず怪物のそれを直視し、瞳と瞳が対をなしていた。
アリスは、それぞれの位置でどれだけの時間凍りついていたのか分からなかったが、その間に、この存在が野蛮な外見をしている一方で、その精神は高潔で、彼女の故郷の惑星の一部の存在と似ている、親近感を感じる存在であることを理解していた。彼女は本能的に手を伸ばし、足が彼女をその存在に近づけ、目の前に存在する何かと繋がりたいと願い、理解しようと願った。
その触れた感じは冷たいと同時に暖かかった。まるでその存在自体が感情の渦、悲しみと愛と憎しみと希望で構成されているかのようだった。ゆっくりと確実に、その影のような存在は形を整え始め、無形の影から、まあ、アリス自身それをどのように表現すればいいのか正確には分からないが、おとぎ話のドラゴンと狼の混合のような姿へと変貌した。
最後に黒い霧が消えたとき、アリスはついに微笑んだ。そして、彼女はその巨大な獣の頭に手を置いた。「あなた、ただ誰かと話したかっただけだったのね…」
彼女がその言葉を終える前に、一つのエネルギー弾が獣に命中し、その体は一瞬の間に衝撃から仰け反り、アリスを一方に押しのけ、すぐに高い警戒態勢に戻った。その全身が、攻撃を仕掛けようとしている者たちに向かって移動し、その影のような霧は再び、明確な形状から再び不明瞭な状態に戻った。
「しっかりしてくれ、マダム」と、馴染みのある声で影のような人物の一人が叫んだ。「今の一撃には十分な力をこめてなかったみたいだよ。」
「うるさいよ、マッドハッター」とダッチェスが反撃した。「私はその子を助けようとしただけさ。次の一撃で確実に仕留める。」
「やめて!」とアリスは叫びながら、対立する両者の間に飛び込み、腕を大きく広げた。まるで彼女を庇うかのように押しのけられてからようやく立ち直ったばかりだ。
「邪魔をしないでくれ、おバカな子よ。そいつをどうにかしないと、私たちは皆死ぬよ。」ダッチェスとマッドハッターは二人とも一斉に低く唸った。
…
アリスは堂々と立ち続けた。
「いいえ、これは侵略次元の存在じゃない。これは…これは…」アリスは獣の方を振り返り、前にいる二人の人物に対して反抗的な視線を戻した。「…彼は私たちの同類なの。」
船の日照りシミュレーターからの人工の光が彼女の部屋を照らし始めると、アリスはそっと目を覚ました。いつもの骨の髄まで凍るような悪夢と、それに伴う罪悪感や憂鬱から解放された、久しぶりの爽やかな目覚めだった。実際、わずか数時間前に彼女が感じていた感情の嵐とそれによる肉体的および精神的な負担にもかかわらず、彼女は妙に穏やかな気分を味わっていた。
「・・・昨日のことが全部夢だったりしないよね?」不吉な考えが彼女の頭をよぎった。先日の体験全てが彼女のボロボロな精神を守るために自分の想像力が生み出した妄想だったとしたら・・・。しかしその疑問は、彼女の部屋の四隅の一つに一瞥すると瞬時に解消された。そこには、前の晩に追いかけ、出会い、友達になった存在が横たわっていた。
目をこすりながら、アリスは静かにベッドから滑り出し、彼を起こさないように注意しながら新しい友人の方へとつま先立ちで歩み寄った。彼は確かに奇妙で、これまで彼女が出会ったことがない存在だった。しかし、それは他のアークの乗船者の多くに対しても同じことが言えた。
彼女がわずか四歩踏み出したところ、その獣は突然動き始めた。頭を持ち上げ、アリスを見下ろした。彼女は驚いて、半歩後退した。少しの間をおいて、「お、おはよう、ジャバウォックさん」と戸惑いながらアリスは言った。彼も含め、昨夜の面々とはそれぞれ名前を交換したが、彼女の部屋への帰り道では他にはあまり話せなかったことを思い出し、改めて緊張してしまう。

「おはよう、少女よ・・・いや、アリス・・・」、幽霊のような存在はやさしげな低音で答えた。頭を垂れて感謝の意を示しながら、「君の助けがなければ、私は消えていただろう。感謝する。」と付け加えた。ジャバウォックの話し方は礼儀正しく、やさしく、心地よかった。彼の凄まじい外見とは一致しないものだったが、見かけによらずとはこのことだ。
数時間前、あの薄暗い行き止まりの通路で彼に接触したときと同様に、少女は再び手を伸ばし、ジャバウォックの垂れた頭に手のひらを当てた。今回彼女が感じた感覚は、愛情深く温かく、とても心地よかった。彼女は優しく微笑み、残っていた疑念や不安は消え去ってしまった。
・・・
「そんな不機嫌な顔をしないでくれ、マダム」と帽子屋がため息をつきながら言った。アリスの部屋のすぐ外で隠れていた彼とダッチェスはその場から去っていく。「これこそ最善の結果じゃないか。」
「ふん、別に不機嫌なんかじゃないよ」と彼女はキッパリと答えた。「昨晩、徒労に走り回された上に、お人よしな小娘の見張りを一晩中する羽目になって体中が痛むだけさ。それに腹も空いている。」
その見張りを提案をしたのが彼女自身だったことを今指摘するのはやぼだと帽子屋は理解していた。ドライな彼女しては珍しいその優しい提案に対し、緊迫した状況の中で身を挺した若い少女の言葉と優しさに感動したのは自分だけではなかったようだと帽子屋は心の中で笑みを浮かべた。
二人は久しぶりに未来へ一筋の希望を感じていた。
■原作設定からキャラクター解説
◯アリス
地球によく似た文明を持つ世界で生まれ育った、強大な力を持つ覚醒者(超能力者)。
故郷が侵略次元の攻撃にさらされた時、その力を振るう覚悟が無かった事を後悔し、“復讐者たちの船・次元航行大陸船アーク”に乗り込み、異世界を渡る永遠の戦士となる。
◯マダム・ダッチェス
侵略次元に滅ぼされた異世界の生き残りであり、戦士。強靭な肉体と精神を持つ、アリスの戦士としての師。
◯マッドハッター
アリスを支える仲間達“A7”のメンバー。本人曰く「奇術師」だが、限定的ながら時間と空間を自在に操る彼の技は、魔法以上に強力な力となる。
飄々とした振る舞いをしつつも、アリスと仲間達を常に気にかけている。
◯ジャバウォック
侵略次元との激闘の末に滅んだ、竜の世界の生き残りの戦士。
肉体を失っており、強靭な精神エネルギーだけで現世に留まっていた、いわゆるゴースト。
この物語の後にA7のメンバー、“チャシャ猫”の広大な精神世界の中に居場所を見出し、普段はそこで眠る事となる。(緊急時にはどのメンバーの精神にも“移住”し、行動をともにすることができる。)
仲間達の危機には嵐の如き念動力を持つエナジー・ゴーストとして実体化し、侵略次元との戦いにおける最終兵器として活躍する。